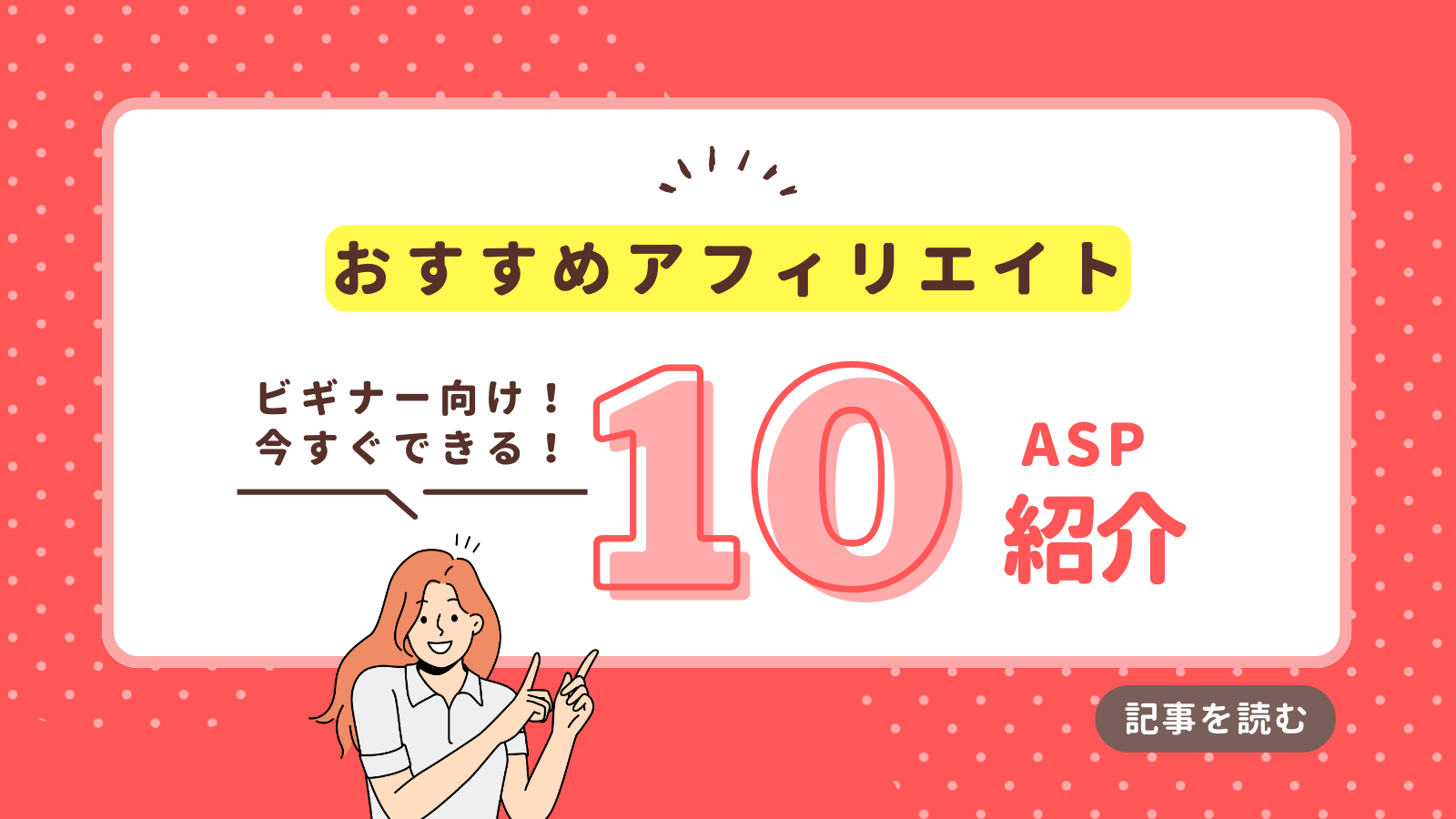Webライターに興味を持って色々調べていると、「Webライターなんてやめといた方がいい!」という言葉を見かけます。
僕自身、webライターを始める前に調べていて、そんな言葉をたくさん見て、本当にやるべきかを迷いました。
そこからWebライターとして様々な案件を請け負い、それなりに酸いも甘いも経験した今。「Webライターなんてやめとけ」の意味を、良くと悪くも理解できました。
結論から言えば、WEBライターが稼げたのは昔の時代の話。生成AI時代に人が手動でライティングで稼ごうというのは正気の沙汰ではないです。
本記事では、そんな『Webライターやめとけ論争』と、良いところと悪いところについて解説していきます。
「Webライターはやめとけ」と言われる理由

そもそもWebライターとして仕事することが、何故これほど否定されるのか。
その理由は、主に以下の4つに集約されます。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
稼げない
Webライターを始めたばかりの頃は、まだ経験も実績もゼロの状態です。
依頼するクライアントからすれば、安心して任せられるのは中堅以上のWebライター。
その結果、なかなか案件が回ってこず収入に繋がりません。
また、高額な案件というのは全体から見るとそこまで多いわけではなく、高額な場合はそれに応じて難易度が高いもの。
そうなるとどうしても安価な案件で稼ぐことになるので、いきなり大きく稼ぐのは非常に難しいです。
Webライターをやろうとするのは、文章を書くことが好きというより、何かに縛られず自由に働いてお金を稼ぎたいという人が多いので、思っているより稼げないことを知るとやめておこうとなってしまうのです。
納期のプレッシャーがきつい
クライアントから依頼される案件には、納期が設定されています。
Webライターの諸事情によってある程度融通してもらえることもありますが、仕事なので原則として厳守です。
自分が好き勝手に書いていつでも投稿できるブログと違い、「ここまでに完成させて提出しなければならない」という状況は、やはり精神的なプレッシャーがあります。
順調に進められる場合は問題ありませんが、なかなか筆が進まない時は焦りと不安が襲ってくるのは避けられません。
会社のノルマから解放されたくてWebライターになったのに、それと同じような苦しみを背負うので、やめてしまう人も多いです。
手間と時間がかかりすぎる
Webライターの仕事は、簡単に稼げたり結果が伴うものではありません。
むしろ泥臭く着実な作業が必要な割に、なかなか稼ぎや評価に繋がらないことも多々あります。
つまりある程度の成果を出せるまでには、手間と時間がかかるということ。
Webライターでラクをしようという魂胆を多かれ少なかれ持っている人は、それとはかけ離れた実態に失望するのです。
健康に悪い
Webライターの仕事は、パソコンとネット環境さえあれば、いつでもどこでもできる仕事です。
しかし反面、ほとんど動かずパソコンに向き合い続けるので、健康には非常に悪いと言えます。
肩こりや腰痛、ストレートネックなど身体の不調が出ることは宿命とも言えるかもしれません。
デスクワークである以上仕方ありませんが、これもWebライターは辞めておくべきという理由の1つに挙げられるでしょう。
Webライターの良いところ

Webライターの良いところはたくさんありますが、その中でも以下の3つは個人的にも特に良いと思える点です。
いつでもどこでも仕事が可能
既に触れた通り、Webライターはパソコンとネット環境があれば、それだけで仕事が進められます。
家でもカフェでも自分の好きな場所で、朝でも夜でも自分の好きな時間に、自由にやれるのです。
通勤ラッシュに巻き込まれて不快な朝を過ごす必要も、体調の悪い日に無理して仕事をする必要もありません。
Webライターとして生計を立てられるようになれば、時間と場所の縛りから解放されるというのは、生きていく上で嬉しいことではないでしょうか。
もちろんWebライターだけの特権ではありませんが、誰でもできる仕事という点で、有力候補と言えると思います。
Webライティングスキル以外も身に付けられる
Webライターは記事を執筆するのが主な仕事ですが、それだけではありません。
クライアントとの交渉、記事の元となる情報のリサーチなど、身に付くスキルはWebライティングに留まらないということです。
つまりWebライターをやっていると、様々なスキルが身に付いて、そこからキャリアアップが可能となります。
例としてディレクターやコンサルタントなど、より専門的なスキルが身に付けられる必要な職種へジョブチェンジするのもアリでしょう。
Webライターから多くの門戸が開けるのは魅力的ですね。
面倒な責任や人間関係に振り回されない
Webライターは基本的に単独業務です。
1人では賄えない部分もありますが、責任を負う範囲は良くも悪くも自分がやったところだけ。
他人と関わる必要性もあまりなく、最低限のコミュニケーションが取れれば支障は出ません。
なので仕事をする上で、責任もコミュニケーションもごく僅かな狭さで済みます。
会社員として、そうした面倒で理不尽なことに辟易してしまった人にも、Webライターはおすすめです。
Webライターの悪いところ
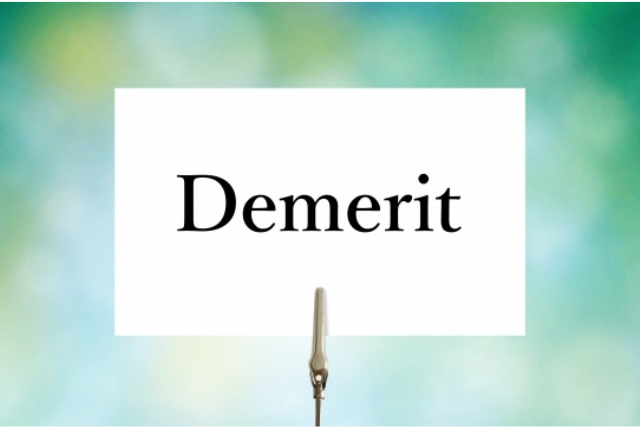
Webライターとしてやっていくのは、良いことばかりではありません。
以下の3点は注意しておくべきでしょう。
稼げるまでに時間がかかる
Webライターに依頼される案件は、報酬額が低いものが多くあります。
もちろん高収入が得られる案件もありますが、多くの人が集まるので、自分が請け負えるかはクライアント次第。
つまり稼ぐためには、そういった高報酬案件をやるか、できなければ低報酬案件を地道にやっていくしかありません。
ある程度経験と実績を作っていけば、クライアントから高報酬案件のオファーをもらえるようになりますが、そこまでのWebライターになるには時間がかかります。
すぐに大きく稼げないのは、Webライターの悪いところと言えるでしょう。
クライアントが納得しないと案件が完了しない
Webライターはクライアントからの依頼を遂行することになります。
そして完成したらクライアントへ提出し、問題なければ完了…という流れです。
しかし、もしクライアントの意に沿ぐわない点があれば、その都度修正対応をしなければなりません。
そしてそれは、クライアントが納得するまで行われます。
指示が細かく面倒なクライアントだと、修正に手間と時間を取られて、割に合わない仕事をさせられることに。
なのでそうしたクライアントに当たらないように、慎重に案件を確認することが求められます。
クライアントが完了とみなさないと報酬が支払われないので、Webライターの立場がどうしても下になってしまうのは嫌なところですね。
稼働しないと収入は得られない
Webライターでどれだけ稼げるかは、どれくらい稼働できるかによります。
ブログや投資のように稼働せずとも自動で稼げる仕組みを作ることはできないので、やらなければ収入はゼロです。
Webライターの仕事自体は時間も場所も選ばず可能ですが、稼働し続ける必要があります。
そのため、もし体調を崩して稼働できなくなったら、その分収入が減るということ。
会社に雇われているWebライターでないと、基本的にその間の保障が何もないのは悪いところです。
生成AI時代にWebライターがライティングで稼ぐのは無理

ここまでメリット・デメリットを見て、ライティングを始めてみようと感じた人もいるかもしれません。しかし、それでも僕は「Webライターなんてやめとけ」と主張します。
それは生成AIの存在です。
生成AI技術が急速に発展する現代において、多くのWebライターが自分の職業の将来性に不安を感じています。特に「ChatGPT」や「Claude」などの高性能な生成AIの登場により、「AIがライターの仕事を奪うのではないか」という懸念が広がっています。
まず、生成AIとは何かについて簡単に説明しましょう。生成AIとは、大量のテキストデータを学習し、人間が書いたかのような文章を作成できる人工知能のことです。最近のモデルは驚くほど自然な文章を生成でき、質問に答えたり、記事を書いたり、さまざまな形式の文章を作成したりすることができます。
これらの技術の登場により、Webライティングの世界は大きな転換点を迎えています。かつては人間のライターだけが担っていた役割の一部を、AIが担うようになってきているのです。では、この状況下でWebライターが従来通りの方法で稼ぎ続けることは本当に不可能なのでしょうか。
残念ながら、従来型のWebライティングだけで安定した収入を得ることは、今後ますます難しくなっていくでしょう。
まず第一に、生成AIの文章生成能力は日々進化しています。基本的な情報提供や簡単な説明文、一般的なトピックについての記事などは、AIが短時間で作成できるようになっています。特に「何々とは何か」といった基礎的な説明記事や、「○○の方法」といった定型的なハウツー記事などは、AIが得意とする領域です。このような基礎的な記事作成の依頼単価は既に下落傾向にあり、今後さらに厳しくなることが予想されます。
第二に、AIによる文章生成のコストは人間のライターと比べて圧倒的に低いという現実があります。例えば、AIを使えば数百円程度で複数の記事を短時間で作成できるのに対し、人間のライターに依頼する場合は一記事あたり数千円から数万円のコストがかかります。コスト意識の高いクライアントやコンテンツマーケティング会社が、AI生成コンテンツを活用する流れは今後さらに加速するでしょう。
第三に、検索エンジン最適化(SEO)の世界でも変化が起きています。以前は「キーワードを適切に配置した記事を大量に作成する」というアプローチが通用していましたが、Googleのアルゴリズムは進化し、コンテンツの質や独自性、専門性などを重視するようになっています。AIが生成した似たような内容の記事が増えることで、差別化が難しくなり、単純なSEO記事の価値は低下していくでしょう。
また、AIツールの普及により、専門知識がなくても誰でも簡単に記事を作成できるようになったことで、Webライティング市場への参入障壁が大幅に下がっています。これにより競争が激化し、単純な記事作成だけでは十分な収入を得ることが難しくなっているのです。
こうした状況を踏まえると、従来型のWebライティング、つまり「クライアントから依頼を受けて一般的な情報記事を書く」というスタイルだけで生計を立てることは、今後ますます厳しくなるでしょう。特に初心者ライターや、特定の専門分野を持たないライターにとっては、価格競争に巻き込まれるリスクが高まっています。
これからの生成AI時代のWebライターに求められるのは、従来の「文章を書く能力」だけではなく、専門知識、独自の視点、戦略的思考能力、AIツールの活用スキルなど、より総合的なコンテンツプロデュース能力です。
しかし、こうした変化に適応するためには、相応の努力と時間が必要です。特定分野の専門知識を身につけるには何年もの学習や実務経験が必要ですし、コンテンツ戦略の立案・実行能力を磨くためには、マーケティングやビジネスに関する理解も欠かせません。
また、AIツールの活用スキルを身につけることも重要です。効果的なプロンプト(AIへの指示)の書き方や、AIが生成した内容を適切に編集・改善する方法など、AI時代ならではのスキルを習得する必要があります。
こうした新しい能力を身につけるためには、継続的な学習と自己投資が不可欠です。専門書を読んだり、オンラインコースを受講したり、実践を通じてスキルを磨いていくことが大切です。同時に、自分だけの「強み」を明確にし、それを軸にしたブランディングを行うことも重要になってきます。
結論として、生成AI時代において、従来型のWebライティングだけで稼ぎ続けることは確かに難しくなっています。しかし、AIにできないこと、AIと差別化できる領域に焦点を当て、自分自身をアップデートしていくことで、新たな可能性を見出すことができるでしょう。
これからのWebライターは、「AIと競争する」のではなく、「AIと共存し、AIを超える価値を提供する」という姿勢が求められます。それは決して簡単な道ではありませんが、変化を恐れず、積極的に新しいスキルや知識を吸収していく姿勢があれば、生成AI時代においても活躍の場を見つけることができるはずです。
ただし、初心者の方々には正直にお伝えしたいことがあります。従来のような「簡単に始められて、すぐに収入が得られる」ようなWebライティングの時代は終わりつつあります。これからのWebライティングは、より専門性が高く、より戦略的な思考が求められる職業へと変わっていくでしょう。その変化に適応できる人だけが、この業界で成功していくことができるのです。