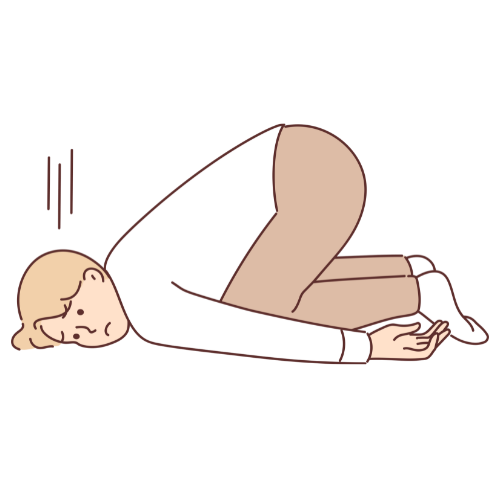近年、YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームの爆発的な人気に伴い、「動画編集者」という職業に注目が集まっています。在宅でできる、特別な資格が必要ない、クリエイティブな仕事といった魅力から、多くの人が動画編集の世界に飛び込んでいます。
しかし、実態はどうでしょうか?「簡単に稼げる」というイメージとは裏腹に、市場は既に飽和状態で、仕事の獲得が難しくなっているという声も増えています。
この記事では、動画編集市場の現状と、特に初心者が直面する厳しい現実について詳しく解説します。
マジで動画編集はオワコン。いくら編集技術を磨こうと、スクールに通っても稼げない。大事なのは、売れる仕組みを知ること。『集客→商品→販売』の流れ。実際に、これを学んでから変わった。売れる仕組みを知らず編集技術を磨くのは、サッカーでスパイクを履かず試合に出ることと同じ。
— いっせい|動画編集×SNSマーケ (@issei_Marketer) January 15, 2025
動画編集者が増えすぎている現状
参入障壁の低さがもたらす過剰供給
動画編集の魅力の一つは、比較的低い参入障壁です。パソコン一台と編集ソフトがあれば始められるため、特に新型コロナウイルスの流行以降、在宅ワークや副業として動画編集に参入する人が急増しました。
無料や低価格の編集ソフトも充実し、オンライン上には無数の動画編集チュートリアルがあります。YouTubeで「動画編集 初心者」と検索するだけで、数万本もの解説動画がヒットします。これらの要因が、市場への新規参入者を増加させる一因となっています。
副業としての動画編集者の増加
正社員として働きながら、副収入を得るために動画編集を始める人も急増しています。本業の給料があるため、低単価の仕事でも受注する傾向があり、結果として市場全体の単価下落を招いています。
クラウドソーシングサイトやSNSでの動画編集の募集に対して、瞬く間に多数の応募が集まる状況は、もはや珍しくありません。一つの案件に対して数十人、時には百人以上が応募するケースも少なくないのです。
『もうショート動画編集で稼げない理由がこの動画で解説されています。』
✅なぜショート動画編集市場がオワコンなのか?
✅ショート動画編集者が月30万円稼ぐには 具体的に何をすればいいか
✅無料でTikTokノウハウをつける方法(動画の最後でプレゼント)を話しています。… pic.twitter.com/sxM469rEwm
— ポール|億超え動画編集プロデューサー (@P_TikTokschool) February 6, 2024
動画編集の仕事を取る難しさが爆上がり
初心者向け案件の競争激化
動画編集の仕事は、大きく分けて「初心者向け」と「経験者向け」に分かれます。初心者が最初に目指すのは当然、初心者向けの案件です。しかし、その競争率は想像以上に高いものになっています。
例えば、「簡単なカット編集のみ」「BGMの挿入」「テロップ入れ」といった基本的な作業のみの案件には、同じように仕事を探している初心者が殺到します。特にコストを抑えたいクライアントは、経験よりも単価の安さを重視する傾向があり、結果として単価の下落競争が起きているのです。
低単価の現実
初心者向けの案件の多くは、非常に低単価です。例えば、10分程度の動画編集で3,000円〜5,000円、時給換算すると最低賃金を下回るケースも珍しくありません。中には「1本500円」といった破格の案件も存在します。
このような低単価の背景には、海外の低コスト人材との競争もあります。フィリピンやインドなど、生活コストの低い国の編集者と直接競合するため、日本の生活水準を考えると非常に厳しい価格競争を強いられるのです。
ポートフォリオがない初心者の苦悩
初心者が直面する最大の壁の一つが、「実績がないこと」です。クライアントの多くは、過去の作品や実績を見て発注を決めます。しかし、初めて動画編集の仕事を探す人には、当然ながらプロとしての実績がありません。
この「実績がないから仕事がもらえない」「仕事がもらえないから実績が作れない」という悪循環は、多くの初心者を挫折させる要因となっています。
生成AIにより動画編集の仕事は完全にオワコン化へ
SNSの短尺動画化による影響
TikTokやInstagramのリール、YouTubeのショート動画など、短い動画コンテンツの人気が高まっています。これらの短尺動画は、凝った編集よりもコンテンツの面白さや新規性が重視される傾向にあり、専門的な編集スキルの価値が相対的に低下している側面もあります。
また、各プラットフォームが提供する簡易編集ツールの進化により、クリエイター自身が基本的な編集を行うケースも増えています。
AI編集ツールの台頭
さらに深刻な脅威となっているのが、AI技術を活用した自動編集ツールの急速な発展です。音声からテキストを自動生成してテロップを入れたり、不要な部分を自動でカットしたりする技術は、年々精度を高めています。
現在でも、簡単なカット編集やBGM挿入、基本的なテロップ作成といった作業は、すでに初心者向けのAIツールで実現可能になっています。例えば「Descript」や「RunwayML」などのツールは、音声からテキストを自動生成し、それを基にテロップを作成したり、不要な部分(「えー」「あの」などの言い淀み)を自動的に検出して削除したりする機能を持っています。CapCutのようなアプリは、テンプレートを選ぶだけで見栄えの良い動画を簡単に作成できるようになっています。
このような技術の進化は、始まったばかりです。今後5年から10年の間に、AIは動画編集の複雑な作業も習得していくでしょう。例えば、「この部分をより感動的にして」「YouTubeで人気が出るような編集スタイルにして」といった曖昧な指示だけで、AIが適切なエフェクトやトランジション、音楽、カット割りを選択し、プロレベルの編集を行うことが可能になるかもしれません。
特に危機に立たされているのは、基本的な編集スキルだけで勝負している初心者の動画編集者たちです。
現在でも、クラウドソーシングサイトには「動画のカット編集だけで5,000円」「テロップ入れのみの簡単な作業」といった低単価の仕事が多く出回っていますが、これらの仕事は真っ先にAIに置き換えられる可能性が高いです。クライアントにとっては、人間の編集者に依頼するよりも、月額制のAIツールを使用する方が、コスト面でも時間的にも効率的になるでしょう。
さらに、生成AI技術の進化により、編集だけでなくコンテンツ自体の作成も自動化されつつあります。例えば、テキストから映像を生成する技術(Text-to-Video)は、既に実用段階に入っています。「海辺で走る犬の映像が欲しい」と入力するだけで、AIがリアルな映像を生成できるようになれば、素材の撮影自体が不要になる場面も増えていくでしょう。
企業の視点からも、コスト削減の圧力は強く、人間の編集者を雇うよりもAIツールを導入する方向に進む可能性が高いです。特に中小企業やスタートアップにとって、プロの編集者に高額な報酬を支払うよりも、月額数千円から数万円程度のAIツールを使用する方が経済的です。
また、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームが独自の編集ツールを進化させることで、クリエイター自身が編集者を必要としなくなるシナリオも考えられます。既にYouTubeは自動字幕生成やサムネイル候補の自動作成機能を提供していますが、将来的には「この素材からバズる動画を自動生成」といったサービスも登場するかもしれません。
アニメーションやモーショングラフィックスの分野でも、AIの進出は始まっています。例えば、「Runway Gen-2」のようなツールは、静止画から動画を生成することができます。将来的には、「このキャラクターが踊るアニメーションを作って」という指示だけで、高品質なアニメーションが自動生成される日が来るでしょう。
イケハヤ先生、直近のYouTubeで「【要注意】AIでオワコン化する人気副業7選」という動画をアップしていたんだけど、「動画編集」とか「Webライター」とか、数年前に先生がオススメしていた副業ばかりランクインしてて笑う
イケハヤ先生がオススメするものはオワコンになる、という法則は未だ健在だ…
— タコペッティ (@syakaisei) July 9, 2024
もちろん、AIによって完全に人間の編集者が不要になるわけではありません。創造的な表現や、クライアントの感情や意図を深く理解した編集、ブランドの世界観を表現するような高度な編集作業は、まだ人間にしかできない領域です。しかし、その領域は徐々に狭まっていくことは間違いないでしょう。
動画編集市場における「オワコン化」は、一気に訪れるというよりも、段階的に進行していくと考えられます。まず低単価の基本的な編集作業がAIに置き換えられ、次第により複雑な作業も自動化されていくでしょう。そして最終的には、高度なアーティスティックな表現を除いて、ほとんどの編集作業がAIによって行われる世界が来るかもしれません。
変化の波は既に始まっています。現在の動画編集市場は、低単価の仕事への参入者が増えすぎていることに加え、これからAI技術によって単純作業が次々と自動化されていくという二重の課題に直面しています。この状況下で生き残るためには、単なる「技術者」ではなく、「クリエイター」として独自の価値を提供できるかどうかが鍵となるでしょう。AI時代の動画編集者は、ツールを操作するスキルよりも、視聴者の感情に訴えかける編集センスや、クライアントの意図を深く理解する力など、AIが簡単には真似できない能力が求められるのです。
それでも生き残るためには?どうすればいいのか?
専門性と独自性の追求
このような厳しい市場環境の中で生き残るためには、「誰にでもできる編集」から脱却し、専門性を持つことが重要です。例えば、特定のジャンル(料理、旅行、教育など)に特化したり、アニメーション、モーショングラフィックスなどの高度なスキルを身につけたりすることで、競争から一歩抜け出すことが可能です。
クライアントとの信頼関係構築
単発の仕事を繰り返すよりも、特定のクライアントと長期的な関係を築くことが安定した収入につながります。そのためには、納期を守る、コミュニケーションを大切にする、提案力を持つなど、編集スキル以外の部分でも信頼を獲得することが重要です。
例えば、クライアントの目的や意図を深く理解し、単なる「作業者」ではなく「パートナー」として関わることで、他の編集者との差別化が図れます。
継続的なスキルアップ
動画編集の技術やトレンドは日々進化しています。定期的に新しいテクニックを学び、ソフトウェアのアップデートに対応し、最新の動画トレンドを把握することで、常に市場で価値のある人材であり続けることが重要です。
また、編集だけでなく、色補正、音響編集、グラフィックデザインなど、関連スキルを広げることで、「動画制作のワンストップサービス」を提供できる可能性も広がります。
無償でも実績を作る
仕事がなくても、自主制作の動画を作ってポートフォリオを充実させることは可能です。友人や家族の動画を編集したり、趣味の動画を作ったり、無料の素材を使ってサンプル動画を制作したりすることで、実績とスキルの両方を積むことができます。
コミュニティへの参加
動画編集者のコミュニティやフォーラムに参加することで、情報収集や人脈形成ができます。TwitterやInstagramなどのSNSで同業者とつながり、情報交換することも有効です。時には協業の機会が生まれることもあります。
営業力の強化
技術力だけでなく、自分をアピールする力も重要です。魅力的なプロフィールの作成、ポートフォリオサイトの構築、効果的な提案文の作成など、営業面でのスキルアップも怠らないようにしましょう。
まとめ:厳しい現実を知った上で挑戦する
動画編集市場は確かに飽和状態にあり、特に初心者にとっては厳しい環境です。しかし、それは「絶対に成功できない」ということではありません。市場の現実を正しく理解し、差別化戦略を立て、継続的な努力を重ねることで、活路を見出すことは可能です。
単に「簡単に稼げる副業」としてではなく、プロフェッショナルとしてのキャリアを真剣に考え、長期的な視点で取り組むことが重要です。一朝一夕で成功することは難しいですが、情熱と忍耐力を持って取り組めば、厳しい競争の中でも自分の居場所を見つけることができるでしょう。
動画コンテンツの需要自体は今後も拡大していくと予測されています。その波に乗るためには、現在の市場が抱える課題をしっかりと認識し、それを乗り越える戦略を持つことが成功への第一歩となるのです。